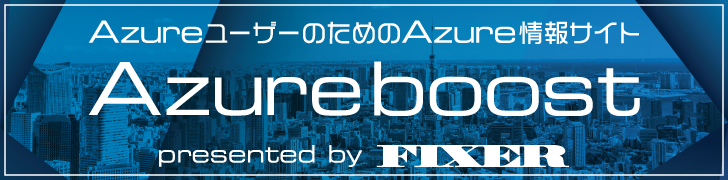「LLMがたくさんあるけれど、結局どれを使えばいいかわからない。」
AIを使っている友人から、そんな声を耳にすることが増えてきました。
私自身、試す機会が多い立場ですが、選択肢が多すぎると「どれを選ぼうか」と考えるだけで時間が過ぎ、結局無難にChatGPTを選んでしまうことが多くあります。
開発する側は「こんな機能もあったら便利だろう」と思って盛り込みがちですが、ユーザーの立場に立つと「多すぎて選べない」という壁が立ちはだかります。
選択肢過多と決断疲労
判断に疲れて選べなくなる
心理学では「decision fatigue(決断疲労)」という概念があります。
人は1日のなかで膨大な判断をしていて、その積み重ねが意思決定の質を落としてしまう。
「今日は黒シャツにするか、白シャツにするか」──そんな小さな判断も積もれば疲労になります。結果、後半の重要な判断は雑になったり、先送りになります。
ヒックの法則とジャムの実験
「選択肢が多いほど、決断にかかる時間は増える」
これはヒックの法則として知られています。
さらに有名な「ジャムの実験」では、24種類のジャムを並べた場合と6種類に絞った場合を比較しました。結果、24種類では試食は多いのに購入率は3%。一方、6種類では購入率が30%に跳ね上がったのです。
つまり、選択肢が多いほど「迷って終わる」リスクが高い。これはそのままプロダクトやサービス利用にも当てはまります。
LLM利用に重なる「選択肢の罠」
今のAI界隈は、まさに「ジャムが24種類並んでいる」状態です。
多様なLLMが次々に登場し、それぞれが強みをアピールしています。
しかしユーザーにとっては違いをすべて理解するのは難しい。
「どれを使えばいいのか」「本当にこの選択で正しいのか」と迷い、結局行動に移せないことも多いのです。
これは、私たちがプロダクト開発で「機能を増やせば使われるだろう」と考えてしまう罠と重なります。実際には、機能を増やすほど迷いが増し、利用が難しくなるのです。
迷わないためのUX設計
では、どうすればいいのか。
- 選択肢を整理する
いきなり全機能を見せるのではなく、段階的に提示する。初心者向けプリセットやおすすめを用意する。 - 推薦する仕組みを入れる
ユーザーが迷わずに済むように、利用シーンに応じて最適なモデルや設定を自動で提案する。 - 決断の負担を軽くする
フィルターやシナリオベースの選択肢を用意して「ゼロから選ぶ」ストレスを減らす。
大事なのは、「ユーザーが悩まずに動ける設計」をどう実現するか、です。
自動で最適化される未来へ
今は「LLMが多すぎて迷う」時代です。
けれど、近い将来は自動で最適なモデルを選び、裏側で切り替えてくれるサービスが当たり前になるでしょう。
大事なのは「選択肢を増やすこと」ではなく、「迷わず使える体験を設計すること」。
それがプロダクトを本当に利用してもらうための鍵になります。
つまり、迷わせない設計こそが最大の価値なのだと思います。
(参考)






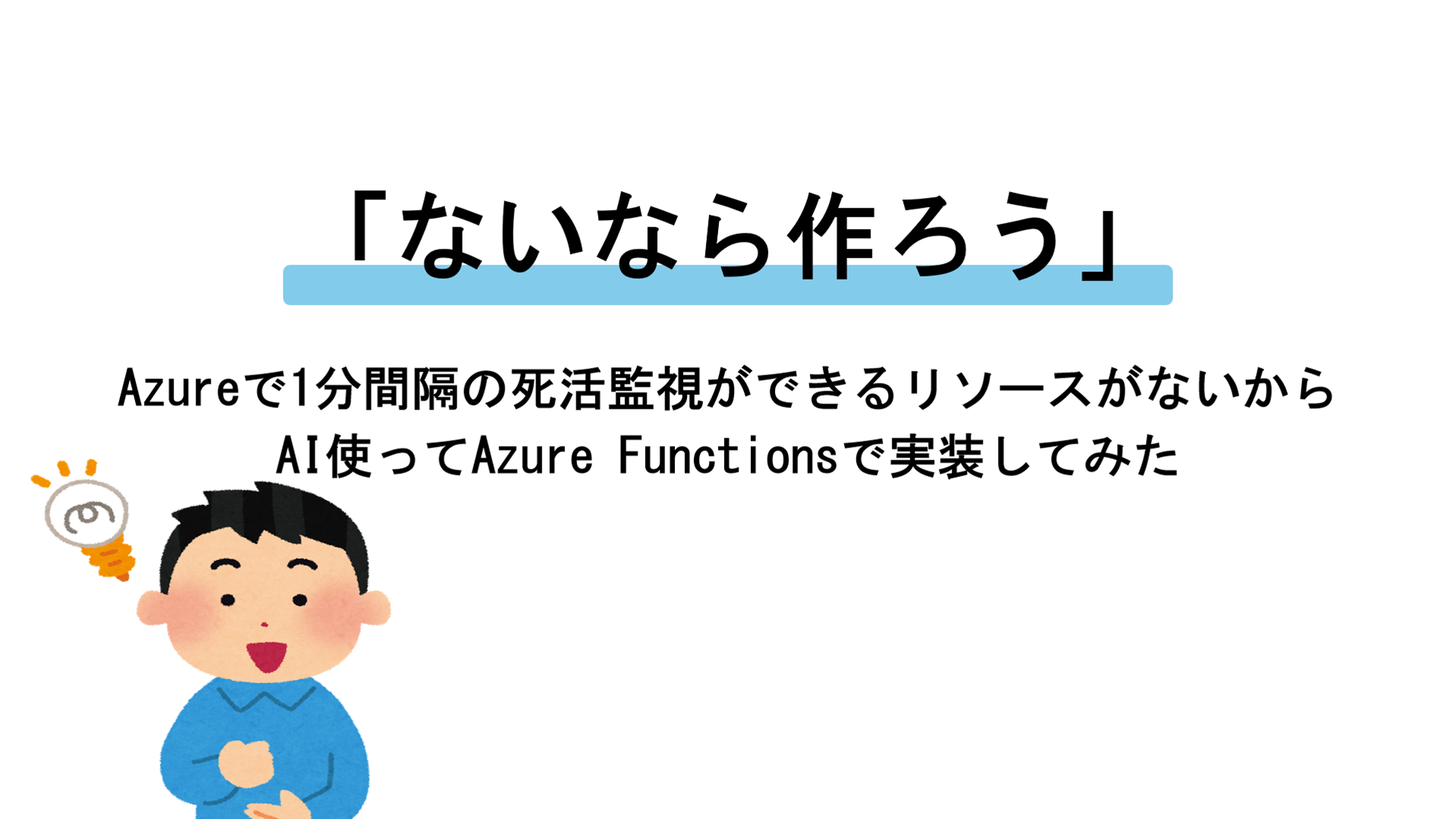

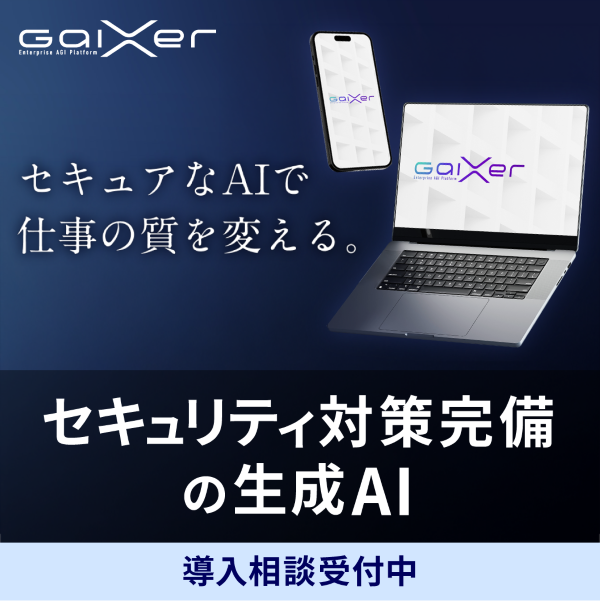
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)