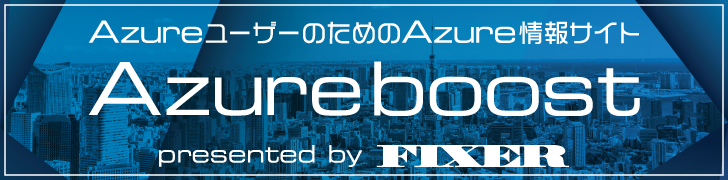自治体総合フェア2025に参加!
2025年7月16日、私は「自治体総合フェア2025」に参加する貴重な機会を得ました。このイベントは、全国の自治体関係者の方々、および自治体向けに革新的なソリューションを提供する企業が一堂に会する大規模なものです。東京ビッグサイトで繰り広げられる熱気あふれる議論と展示は、まさに地方創生と行政DXの最前線を体感できる場でした。
本記事では、イベント参加を通じて得られた知見に加え、限られた時間の中でいかに有益な情報を引き出し、実りある対話を行うかという、コミュニケーションの難しさとその改善策について、自身の体験を交えながら記していきたいと思います。
参加目的
今回このイベントに参加した最大の目的は、自治体とその関連企業が抱える課題や、提供するソリューションに対する解像度を深め、今後の自身の業務に活かしていくことにありました。中でも特に、昨今注目を集める生成AIの自治体への導入における障壁(技術的、予算的、人的、組織的側面など)や、実際に導入が進まない具体的な要因について深く掘り下げることを目標としていました。既存の概念に囚われず、現場のリアルな声を聞くことで、より実践的なアプローチを模索したいと考えていました。
情報を引き出す難しさ:効果的な対話のために
イベント会場での情報収集は、多くの場合、ブースで提供されるプレゼンテーションを聞くことから始まります。しかし、設定した目的、特に生成AIに関する具体的な情報を効率的に得るためには、様々なコミュニケーション上の課題に直面しました。限られた時間の中で、いかに効率的かつ質の高い情報を得るか、という点が重要なテーマとして浮上しました。
1. 強引な展開から生まれる齟齬
経験したこと
当方の主な関心事が生成AIであったにもかかわらず、提示される事業内容が生成AIとは直接関係のないものであった場合、そこから目的とする情報を引き出すことの難しさを痛感しました。私自身、焦りからか、無理にでも生成AIと相手の事業内容を結びつけようと試みました。しかし、その強引な展開は相手に困惑の表情を浮かべさせ、「何を言っているんだ?」というような反応を引き出し、結果として期待する回答は一切得られませんでした。それどころか、無理なこじつけに意識が集中するあまり、相手のプレゼンテーションの本来の内容を十分に理解することが疎かになってしまうという本末転倒な結果を招きました。
改善策
まずは、相手が提供するサービスやソリューションの本質、そしてその背景にある課題意識や意図を深く理解し、自身の知識として吸収することが極めて重要であると痛感しました。その上で初めて、自身の目的である生成AIとの関連性を探り、具体的な活用アイデアや質問へと昇華させることで、より実りのある、解像度の高い議論が可能になると気づきました。また、もし無理に生成AIとの接点を見出せない場合は、その情報を今後の知見としてインプットに留め、無理に会話を深掘りしたり、一方的な提案を行ったりする必要はない、という割り切りも肝要であると学びました。全てのブースで生成AIの情報を得ることに固執するのではなく、幅広い知見を得るという柔軟な姿勢も必要だと感じました。
2. 曖昧な質問による情報の希薄化
経験したこと
相手のプレゼンテーション内容を十分に理解した上で質問を投げかけたにもかかわらず、期待する深掘りした情報を得られないケースが多々ありました。その原因を振り返ってみると、私の質問が往々にして曖昧で抽象的であったことに尽きます。「〇〇についてどうお考えですか?」や「課題は何ですか?」といった漠然とした問いは、相手に具体的なイメージを抱かせにくいため、困惑させてしまうか、あるいは表面的な、一般的な回答しか引き出せない結果となりました。結果的に、深い部分に踏み込んだ示唆を得ることはほとんどありませんでした。
改善策
質問を組み立てる際には、まず相手がすぐに具体的に答えられる範囲の事柄であるか否かを慎重に見極める必要があると感じました。相手がその分野に深く精通している場合であれば、多少抽象的な質問であっても、相手が意図を汲み取り、的確な回答を返してくれる可能性はあります。しかし、相手の関心が疎い領域(例えば、生成AIとは直接関係のない事業を展開する方に対し、生成AIの具体的な活用方法について尋ねる場合など)においては、具体的なシナリオや例を提示し、「もし御社のサービスの〇〇の部分で生成AIを使って✕✕をしたら、どのような点が課題になりそうですか?」「例えば、〇〇といった業務に生成AIを適用した場合、どのようなメリットが考えられますか?」といった形で、相手がイメージを膨らませやすいように工夫することが極めて重要であると痛感しました。
得られた学びと今後の展望
今回の自治体総合フェア参加は、単なる情報収集に留まらず、自身のコミュニケーションスキル、特に「質問力」と「傾聴力」の不足を痛感させられる貴重な機会となりました。この経験から得られた学びは、今後の業務において多方面で活かしていきたいと思います。特に、顧客やパートナー企業との対話においては、相手の状況やニーズを深く理解するための「傾聴」と、的確な情報を引き出すための「具体的かつ示唆に富む質問」をより意識していきます。また、新たな技術やサービスを提案する際には、相手の立場に立ち、具体的なユースケースやメリットを明確に提示することで、より実効性の高い提案を目指します。
自治体総合フェア2025での経験は、私にとって情報収集とコミュニケーションの奥深さを再認識させるものとなりました。この学びを糧に、今後も行政DXの推進に貢献できるよう、研鑽を積んでいきたいと思います。







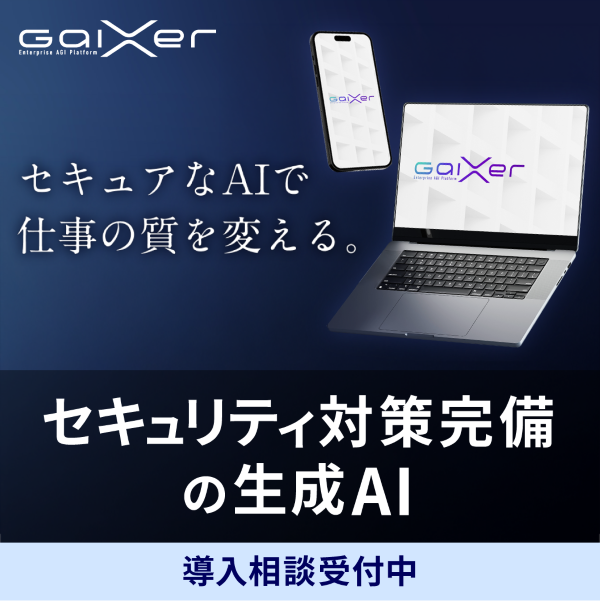
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)