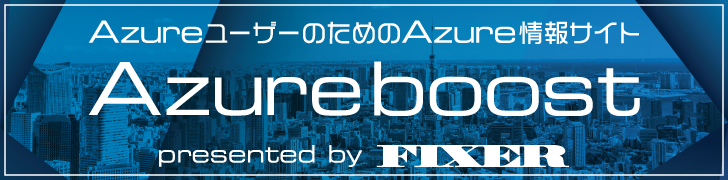はじめに
今回は自治体に関わるプロジェクトでリーダーを務めた経験を、「やりがい」「注意していたこと」「苦労したこと」の3点で整理してまとめます。
もともと、私はFIXERで新卒採用を実施していました。そこから営業とこのプロジェクトリーダーになったという経緯があります。
このプロジェクトは何かというと以下のプロジェクトです。簡単に説明すると「お客様が生成AIサービスを業務に活用し、自ら生成AIを用いて課題解決ができるようになるサポート」です。
もう少し詳しい内容は以下に記載しております。良かったらぜひ見てみてください。
https://fixer.co.jp/news/2025/10/2025_1023_001_japan_center_for_regional_development/
やりがい
まずはやりがいから伝えるのですが、ざっくり5点あります。
- お客様に目の前で喜ばれる
- お客様の悩みを直に聞くことができる
- プロジェクト経由で別のお問い合わせや別の話に発展する
- 社会に対して何かしたと言える
- だんだんとメンバーが自走し始める
1. お客様に目の前で喜ばれる
メンバーがお客様の課題を生成AIで解決し、それをお客様に見せに行った時、驚きと喜びの声が挙がりました。
私自身、その課題を解決した訳ではないのですがこのプロジェクトに関わって良かったと思えた瞬間でした。
すごくシンプルなことでしたが、このために働いているんだなと思えました。
2.お客様の悩みを直に聞くことができる
昨今、課題解決やDX化などがよく聞こえてきますが実際の現場の方の具体的な悩みを引き出し聞くことが少ないように思えます。
ですが、このプロジェクトでは直接、業務の中の悩みを聞くことができるのでその悩みをダイレクトに解決できるというのは良い点だと思います。
解決が出来なかったとしても現場の人と議論し、生成AIで解決できる策を生み出せるのはとても良いです。
3.プロジェクト経由で別のお問い合わせや別の話に発展する
プレスリリースや現場の人との交流を経て活動が認知されてきて、有り難いことで多方面で別のお話が来るようになってきました。
私としては、この活動をより多くの人に知ってもらいたいと思っており、この活動の事例などをオープンに公開したい気持ちがあります。
こういった別のお話に発展するときには、私達のメンバーでできる最大限を持ってお話に望みます。
4.社会に対して何かしたと言える
プレスリリースには、私の名前は乗っていませんがこのプレスリリースが色んな所へ転載されていました。
小さな社会への貢献かもしれませんが、ここまで仕事をしてきてやっと出せたプレスリリースでもあるのでやったなぁと思う反面、これからもっと頑張らないとという気持ちになります。
まずはスタートラインに立てたということはやりがいです。
5.だんだんとプロジェクトメンバーが自走し始める
最初は私からの指示をすることが多かったですが、今はプロジェクトメンバーが自分たちで考え、自分たちなりの答えが出てくるようになりました。しかもめっちゃ的確な答え。
リーダーとしてという大層なことや偉そうなことは言えないですが、お客様を自走できるようにご支援する反面、私らが自走出来なかったらそれは違うだろうなという想いもあったので嬉しいなと思ってます。
円滑にプロジェクトを進める上で注意していたこと
初めてのプロジェクトリーダーということ、しかも私判断がほとんどの役割なので社内外問わず細心の注意を払って業務を進めていました。
社内では、FIXER側の経営層、プレスリリースに関わる部署、生成AIに関わる部署、私がいる部署、全社員への情報発信のざっくり5つ関係を把握し1つ1つ、自分の考えを報告、連絡、相談をしていました。
あらゆる人に相談するということは情報を沢山得られるという点では非常に有用な手段だと思いますが、相談しすぎるとそれぞれの人に常に情報を更新し意見を求める、意見を変えないような自らがんじがらめになる危険性もありました。そのため、この人に情報を発信するということはどこの部署の誰にまで情報はインプットされ、そのインプット情報は真っ直ぐに伝わるか?をこのプロジェクトのゴールから徹底的に考え、行動しました。
このプロジェクトは、社内と社外それぞれで細かい点で認識がズレていたり、変わっていたりする部分がありました。だからこそ、私自身の決める所はキチンと決め、方向性を整理し進めていく必要がありました。
このプロジェクト円滑化の肝は、徹底的な社内外問わない因果関係の把握とそこへの情報発信の粒度とタイミングにありました。
なので注意していたことは、「このプロジェクトを如何に孤立させず、だが固執しないように心がけたこと」ですね。
苦労したこと
正直最初は、とても不安はありました。プロジェクト成功の鍵が自分にある気がしてどこまでできるのかはわからなかったからです。
ですが、自分の知識と足りない知識を分け、その時に手伝っていただいた人に相談することを行い慎重に進めることができたと思います。
苦労したことは2点あります。他にもありますが今回は抜粋しました。
- プロジェクトメンバーとの雰囲気作りと指示
- お客様との距離感
1.プロジェクトメンバーとの雰囲気作りと指示
ここは最も苦労したことです。全員後輩ということもあり、初めは多少の忖度がありました。そのため本音を聞くことが難しかったです。
このタスクはこのメンバーに取って時間のかかることなのか、したいことなのか。今現状不安はないのか。を引き出すことは苦労しました。
対応策としては、私からこのプロジェクトのビジョンを示すこと、今どんな状況でメンバーにどうして欲しいのかを伝え続け議論をしました。
そうすることでただメンバーに指示を行ったとしても花田さんならという言葉の裏も理解した上で求めているタスクのクオリティを超えるものが出てきました。
2.お客様との距離感
私自身、ここは初めての試みでした。なぜならば今まではプレイヤーとして学校の先生やお客様と関わることしかしておらず、タスクを管理するようなマネージャー的な関わり方をしてこなかったからです。
だからどこまでお客様と自分が近づいて交流をすれば良いのか。どうすればFIXERさんではなくプロジェクトメンバーの花田さん、〇〇さんと言ってもらえるのかは悩みました。
対応策としては、主張を控えめにすることを心がけました。これが正しいかは検証中です。
ですが、生成AIの講座などで質問回答にリーダーとしての説得力は出せているかなと思ってます。自負ですが。
まとめ
以上が本題でございました。
結構社内では最近、お酒呑みすぎじゃね。不思議な元気な人としてキャラが通っていますが今回は真面目なブログを書いて見ました。
3年目として業務をしている自覚はなく、ただお客様にできることを全力でしているのでこれからも頑張りたいと思います。






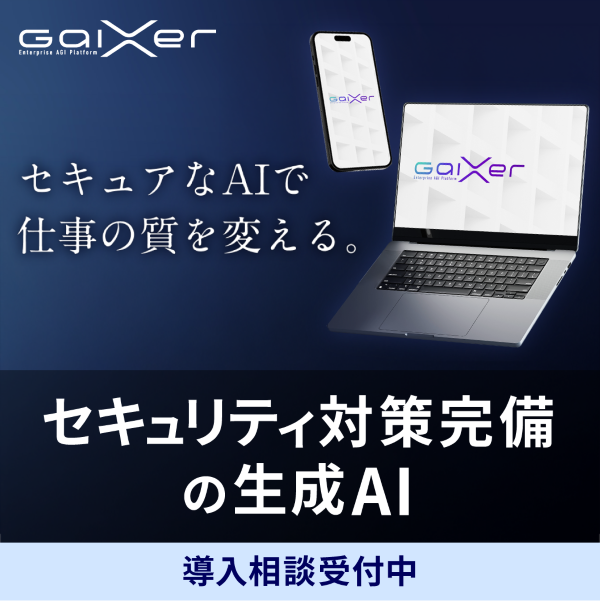
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)