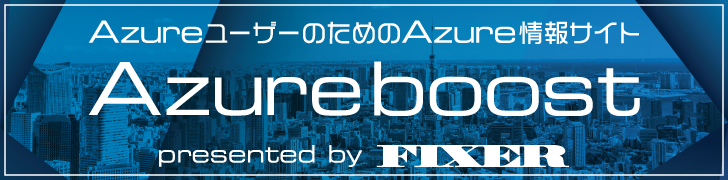初めに
皆さんこんにちは。運用周りでエンジニアをしている相島和貴です。
今日は先日開催された第36回全国高等専門学校プログラミングコンテスト(高専プロコン)で企業側として参加させていただける機会をいただいたので、活躍している高専生の作品や活動お話しさせていただきます!
第36回高専プロコンについて
今年度の高専プロコンは、島根県松江市の「くびにきメッセ」で開催されました。
メインテーマが「水都で作る、未来のイノベーション」 となっており、国宝松江城を中心とした水の都松江を舞台にしたテーマになっています。
課題部門のテーマが「ICTを活用した環境問題の解決」となっており、社会課題を解決するための、高専生の作り上げたプロダクトが発表されました。
会場はブースが設置されている空間(大展示場1)と競技部門も行われたメインステージの空間(大展示場2)の2つに大きく分かれており、会場が両隣で行き来しやすかったです。
今回は大展示場1でブースが設置されていた自由部門と課題部門、大展示場2で行われた競技部門について少しお話しさせてください。
自由部門
自由部門で一番印象に残った作品は、熊本高専(八代キャンパス)のMr.PET(ペットボトルでプラモデル作り)です。
すごかった点
- ペットボトルからフィラメントの成型
- 2D画像から3Dモデルへの変換
ペットボトルからフィラメントの成型に関してはとても感激しました。
私も学生時代に同じことを行う機会があり、一見簡単そうに見えるのですが、、、、実はめっちゃムズイ!!
最初にペットボトルを帯状にカットする必要があるのですが、均一にカットできなかったり、
円形のフィラメントに成型する際の温度調節で、温度が高すぎると巻き取ることができず、低すぎるとめっちゃ細いフィラメントになってしまい、使うことができません。
巻き取るスピードの調節にもよってフィラメントの太さが違ってくるので、一見大丈夫そうに見えても実際に使えなかったなんてこともあります。
これらの問題を解決させて実際の3Dプリンタで問題なく使用できているところを見ると、やっぱりすごいですね!!
課題部門
課題部門で一番印象に残った作品は、豊田高専のエネまるクラフト(デジタルツインで学ぶ再生可能エネルギー)です。
すごかった点
- 環境の実データををダッシュボードだけでなくゲームにも組み込めている
- デジタルツイン型のActive Lerning教材として提供できる
小学生向けの教材として、座学だけでなく実際に動かして体験までできるところがすごかったです。
実際に環境データ(水力・風力・太陽光・地熱)を取得できる機器から送られてきたデータを、Next.jsで作成したダッシュボードだけでなく、Minecraftなど全国の小学生が知るゲーム内の町にリアルタイムで反映できており、完成度が高かったです。
実際に、各エネルギーをオン・オフ切り替えることができ、発電から町のインフラの消費電力を賄える部分と賄えない部分など細部まで工夫して作り上げられていました。また、国際的に人気なMinecraftを用いることで国際展開も期待できるとのこと!!
ダッシュボードでは、電力やCO2削減量などがグラフ化されており、数値的な面でも生徒の考えを深められるといったところまでも考えられていました。
競技部門
今回は競技部門の方も見てきました!
競技部門では、フィールド上に数字が割り当てられたエンティティが散りばめられており、同じ数字をもったエンティティ同士を隣り合わせてペアを作成していき、
全てのエンティティが隣り合わせられた際の、手数によって勝敗が決まる競技になっております。
チームによってはAIの活用を行っていたり、ペアを効率よく作成するためのアルゴリズムの開発のためにGUI(ビジュアライザ)の作成を行っているチームもありました。見ていたところ、AIを使用しているチームではPCの性能差により、精度の差が出ているところもあれば、すべてアルゴリズムを自分たちのチームで構築しているチームもあり会場は白熱していました。
1日目と2日目の準決勝まで、東京高専が強かったのですが、なんと決勝戦において八戸高専が数手差で優勝を勝ち取り、会場は盛り上がりましたね。
ちなみに各試合開始前の待機画面は松江名物のしじみでした(笑)




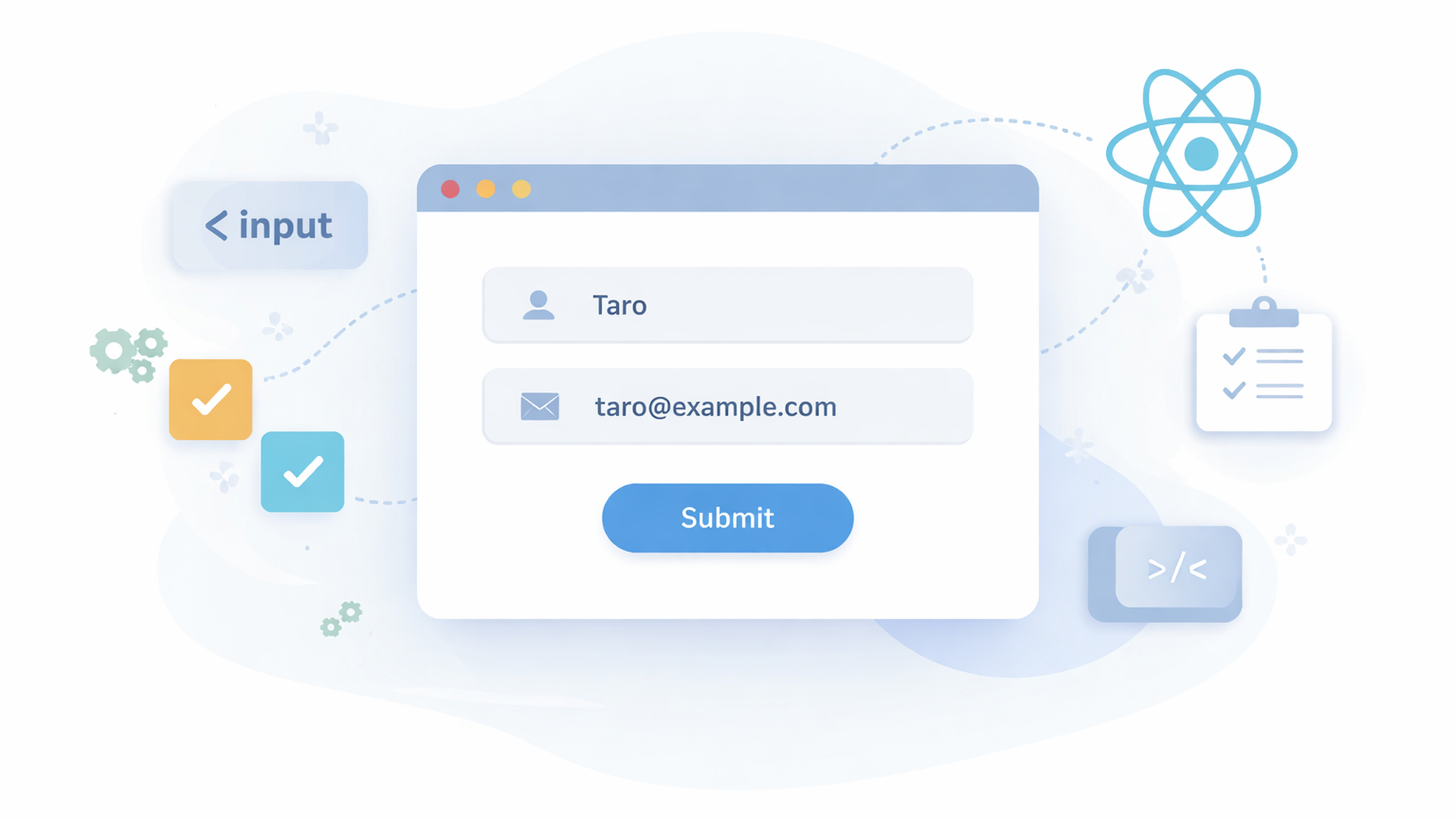



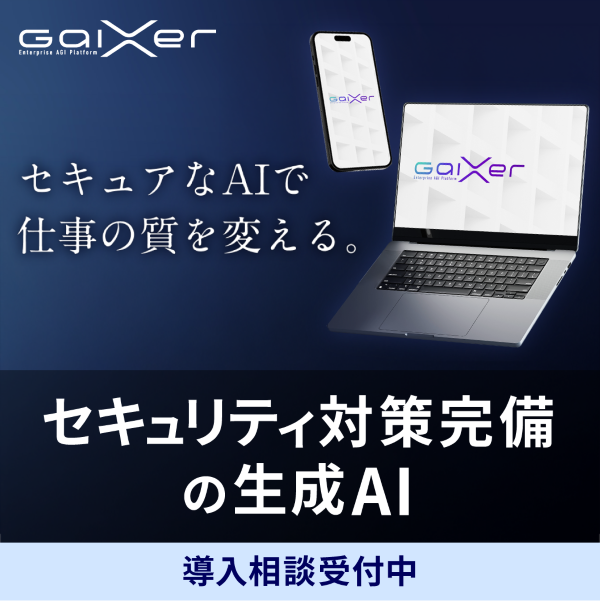
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)