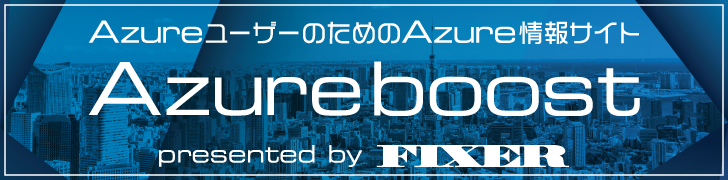こんにちは、はじめまして。2025年にFIXERへ中途入社した平野と申します。
少し長くなりますが、これまでの歩みとこれからの意気込みをご紹介します。
コンサルでの修業時代
- 新卒以来、国内外のコンサルファームで10年以上にわたりビジネス領域のプロジェクトに携わってきました。
- IT案件の経験はほぼなく、経営戦略や組織改革、新規事業など「人」と「仕組み」に関わるテーマを中心に、奔走してきました。
- コンサルの面白さは、様々な業界・課題に向き合いながら、お客様の頭の中にある想いを構造化して形にしていくこと。プロとしての矜持や粘り強さは、今も自分の大切な軸になっています。
テクノロジーへのシフトを決意した理由
コンサル業界でもデジタルの必要性は叫ばれていましたが、最新技術を自ら使い倒す機会は多くありませんでした。そんな中、生成AIの急速な進化に衝撃を受けました。McKinseyは生成AIが世界全体の企業利益を年間4.4兆ドル押し上げる可能性があると試算しており、既に従業員の生産性を66%向上させた事例も報告されています。これほどの技術革新を横目に、旧来のやり方だけにこだわるのは勿体ない――そう考え、コンサルで培ったプロ意識は持ちつつテクノロジーの力で事業を創る側へ舵を切ることにしました。
入社後の日々と思いがけない変化
FIXERに入ってからは、二言目には「生成AIを使って○○しよう」と口にしている自分がいます。資料作成、議事録の要約、アイデア出し…ほとんどの作業にAIを組み込み、以前は何日もかかったタスクが数時間で終わることもしばしばです。先述の調査でも指摘されているように、生成AIは定型業務の自動化や文章作成の効率化など多方面で人間の能力を増幅してくれます。
最近の悩みと「外部メモリ」への探求
一方で、アウトプットの量が自分の記憶容量を超え始めています。コンサル時代と比べると勤務時間自体は少し減ったものの、家に帰るころにはその日のやり取りの一部を覚えていない…。生成AIの可能性は「外部化された記憶」や「認知的オフロード」によって人間の限界を超えると期待されていますが、過度な依存にはリスクもあり、AIに頼り過ぎると本来の判断力や人間らしさが損なわれるという指摘もあります。現実に、日々の膨大な生成物をどのように整理し、必要なときに取り出せるようにするかは目下の課題です。
生成AI+人間のメモリをどう高めるか(私見)
現時点での答えは、「メモリ機能そのものもAIに任せつつ、人間が確認する習慣を持つ」ことだと考えています。具体的には、
- AIツールにタスクや会議の要点を自動で要約させ、日別のダイジェストを作る
- AIが生成した内容に自分なりのコメントを加え、ただの「受け売り」にならないよう意識する
- 忘れたくない要素はAIのリマインダーや日報機能に登録し、帰宅後に必ず見返す習慣をつくる
生成AIは上手に使えば自分の認知能力を飛躍的に拡張してくれますが、依存し過ぎると外部に委ねた記憶が裏切られたときに大きな損失を受けかねません。AIを「相棒」として扱うことと、自分自身の判断や記憶を磨くこと――両輪が必要だと痛感しています。
最後に
生成AIという追い風に乗りながら、コンサルで学んだ「問題を解き、価値を創る」力を掛け合わせれば、従来の7倍以上の生産性を実現できると信じています。テクノロジーと人間力のバランスを探りつつ、仲間とともに爆速で成長し、世の中にインパクトを与える変革を起こしていきましょう。どうぞよろしくお願いします。


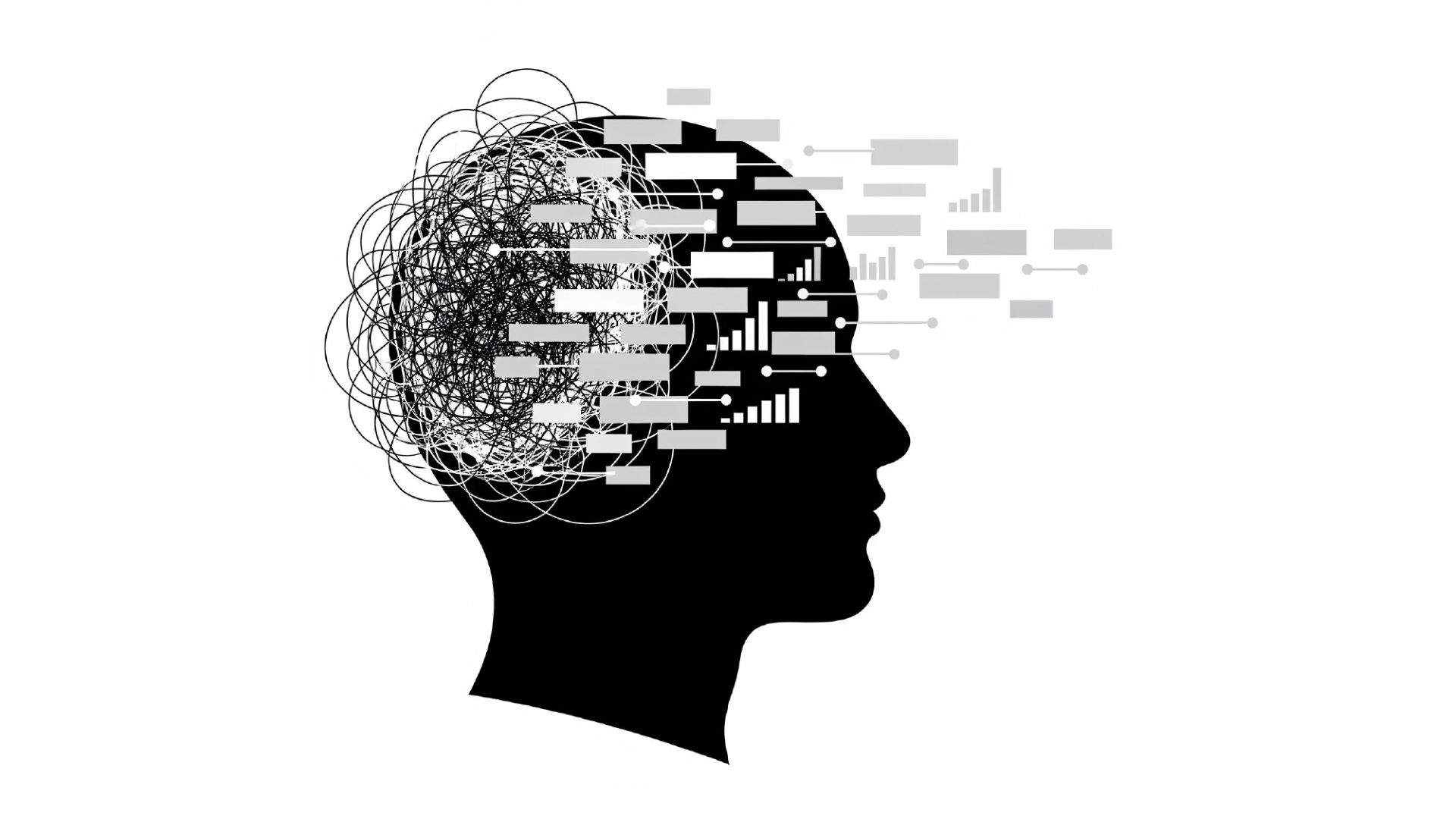




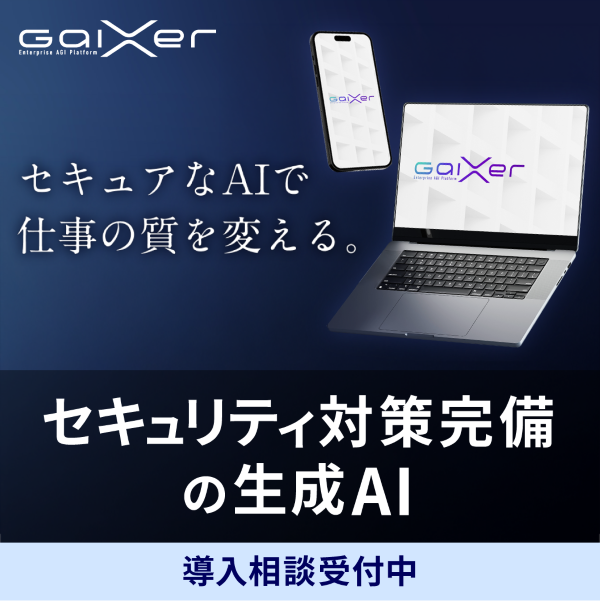
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)