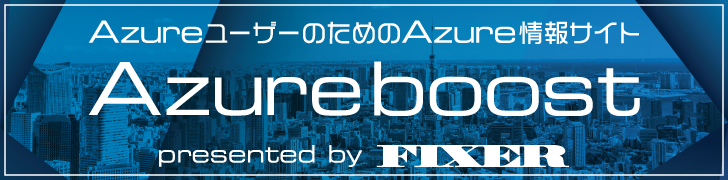誰も望まない「炎上」。けれど、その混乱の中には、組織が成長するための構造のヒントが隠れています。プロジェクトを進めていると、
スケジュールの遅れや要件変更など、思いどおりにいかない場面が必ずあります。
炎上は誰も望みません。
しかし、避けて通ることもできません。
僕もこれまで、いくつかの炎上案件を経験してきました。
その最中はとても「宝」なんて思えません。
けれども振り返ると──あの混乱の中でしか見えなかったことが確かにありました。
最近、エンジニアの友人が言った言葉が印象に残っています。
「炎上は宝ですよ。」
その一言をきっかけに、
“炎上をどう扱えば組織は前に進めるのか”をあらためて考えてみました。
仕組みの綻びが表に出る瞬間
炎上の瞬間、普段は見えなかった仕組みの綻びが一気に表に出ます。
意思決定の遅さ、情報共有の滞り、役割の偏り。
こうした問題は、平常時にはなかなか気づけません。
私たちが業務を進める中でも、
問題が起きて初めて、どこが詰まっていたのかが見える。
炎上は、構造を可視化する“組織の健康診断”のようなものだと感じます。
炎上が示すのは「人」の本質
現場が燃えると、人の動き方が変わります。
タスクが崩れた瞬間に黙って拾う人。
冷静に優先順位を整理して全体を見直す人。
あるいは、プレッシャーに耐えきれず距離を置く人。
こうした行動の差が、チームの信頼関係や実際の役割分担を映し出します。
炎上対応の中で得られるこの“人のデータ”は、
チーム設計を見直すうえで貴重な材料になります。
炎上は、再設計のチャンス
ほとんどの炎上は「誰かの失敗」ではなく、
「想定していたけれど、対応が追いつかなかった」ことから起きます。
だからこそ、炎上のあとには再設計のプロセスが必要です。
- どの情報が遅れたのか
- どの判断が迷ったのか
- どの工程で摩擦が生まれたのか
これらを丁寧に振り返り、仕組みに還元すれば、
同じ炎上は繰り返しません。
炎上を恐れず、早く発見できる文化へ
炎上をゼロにするのは理想ですが、
挑戦がある限り、リスクはゼロになりません。
大切なのは、「炎上を防ぐ文化」ではなく、
「炎上を早く見つけ、立て直せる文化」を育てることです。
プロジェクトの進行状況を見える化し、
小さな異常を早期に共有する。
その積み重ねが、次の炎を大きくしない一番の方法です。
「炎上は宝」──起きた火を次に使える組織が強い
炎上は良いことではありません。
しかし、その中には次の成長につながる素材があります。
火を完全に避けることよりも、
燃えた跡をどう使うかが組織の成熟を決めます。
炎上を宝に変えられるチームは、
挑戦を止めずに前に進めるチームだと思います。







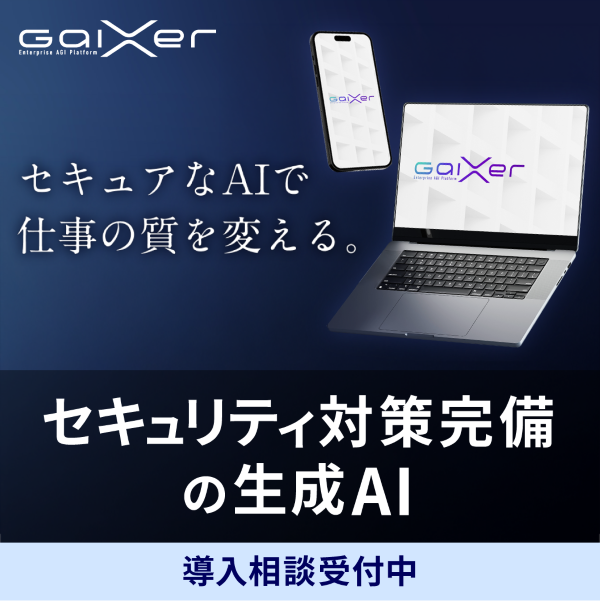
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)