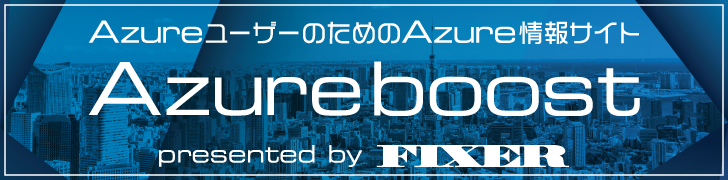なぜ活用されない? 生成AI導入を阻む「3つの見えない壁」
庁内に生成AIが導入されたものの、活用しているのは一部の職員などに限定的になっていないでしょうか。
「なんとなく便利そう」とは思われていても、日常業務への組み込みが「自分事」になっていないケースは多く見られます。
現在、あるプロジェクトでは、「生成AI活用ワークショップ」の企画・導入支援を進めています。
生成AIの進化は著しい一方で、実際の業務現場での活用は、まだ大きなギャップがあることが実態です。そこでは、「活用が進む人」と「踏み出せない人」の間に、明確なギャップが見られました。
この背景には、単なる個人のITスキルとは異なる、組織特有の「見えない壁」が存在すると考えられます。
- 「セキュリティは本当に大丈夫なのか?」という漠然とした不安
- 「自分の業務の、いったい“何”に使えるのか?」という具体的な活用イメージの欠如
「新しい使い方を覚えることで業務が止まってしまうくらいなら、既存のやり方を続けた方が効率的だ」という、変化への抵抗感
これらの「壁」を前に、多くの職員が活用に踏み出せない状況があります。
もちろん、外部の支援者が一時的なセミナーを開催したり、便利なテンプレート(プロンプト集など)を作成・配布したりすることは可能です。
しかし、その支援(伴走)だけでは、支援が終了した途端に活用が止まってしまい、本当の意味で組織の力になったとは言えません。
重要となるのは、単なる「伴走」に留まらず、支援がなくとも活用が続く「仕組み化」のための工夫を考えることです。
本記事では、この問題意識を起点に、「組織を自走させる」ために必要と考えられるアプローチ(構想)についてご紹介します。
なぜ今、自治体に「自走できるDX」が必要なのか
現在、多くの地方自治体が構造的な課題に直面しています。人口減少、少子高齢化、そして過疎化の進行など、行政サービスの「担い手不足」という深刻な問題を引き起こしています。
同時に、「デジタル田園都市国家構想」に代表されるように、国全体としてDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する要請もあります。限られたリソースの中で、多様化・複雑化する住民ニーズに応え続けるためには、デジタル技術を活用した業務効率化やサービス向上が不可欠です。
こうした状況の中で、生成AIは、これらの課題を解決する「鍵」として大きな期待が寄せられています。定型業務の自動化や職員の高度な判断を支援することで、リソース不足を補い、行政サービスの質を維持・向上させる可能性を秘めているためです。
しかし、どれほど強力なツールを導入しても、その活用が外部からの支援に依存したものでは、継続的な力にはなりません。支援が終了するとともに活用が停滞する「外部への属人化」に陥ってしまえば、真の課題解決には繋がらないのです。
行政が直面する大きな課題に中長期的に立ち向かうためには、ツールを導入すること以上に、組織自らがそれを活用し、改善し続けられる「自走できるDX」の体制を築くことが重要になってきています。
組織を「自走」させる鍵は、「教育者を育てる」こと
生成AI活用における理想的な状態は、外部の支援がなくとも、組織が自らの力で活用を推進・改善し続けられる状態、すなわち「自走」できる状態に移行することです。
その実現の鍵となると私たちが考えているのが、組織内部に「教育者」を育て、自律的な活用サイクルを回せるようにすることです。
外部支援者による伴走モデルでは、支援者がいる間は活用が進むものの、その存在が前提となり、結果的に「外部への属人化」を招くリスクが懸念されます。
一方で、内部の職員が「教育者」の役割を担うことで、状況を大きく変える可能性があると期待されます。 一般的に、人に教えるというプロセスは、教える側(職員自身)のツールへの理解度を飛躍的に深める効果があると言われています。
さらに、育った「教育者」が次の「教育者」を育てる循環が生まれれば、組織内に持続的な知識のサイクルを生み出すことに繋がります。
これこそが、単なるスキル研修に終わらない、本当の意味での「人材育成」に繋がるのではないかと考え、国が求める「自律的にDXを推進できる人材」の育成にも直結するアプローチになると期待しています。
「体験」から「仕組み化」へ。自走サイクルを生み出す3つのフェーズ
この「教育者を通じた自走サイクル」を組織に実装していくためには、組織全体が以下の3つの「フェーズ(段階)」を経ていく必要があると、私たちは考えています。
私たちは現在、お客様(組織)がこのフェーズをスムーズに移行できるよう、支援内容を協議しながら進めています。
フェーズ1:体験する(学習者としての経験) まずは組織全体の「見えない壁」を取り払うことが最優先です。 セキュリティへの不安を解消し、ガイドラインを整備した上で、まずは「学習者」として全職員が安全にツールに触れ、「どのようなものか」を体験する機会を作ります。ここで重要なのは、具体的な活用法を学ぶ以前に、心理的なハードルを下げることです。
フェーズ2:人が育つ(教育者側としての成長) 次に、フェーズ1の「体験」で得た知見や成功事例を、職員が自ら「まとめる」段階です。 さらに、その知見を他者に「教える」経験を通じて、職員が「学習者」から「教育者」側へと成長していくことを目指します。 このプロセスこそが、組織内に「自分たちで業務を改善する力」を広げていく起点となると考えています。
フェーズ3:仕組み化(組織としての定着) 最後は、フェーズ2で成長した「教育者」が主体となり、組織全体に活用を定着させる段階です。 例えば、蓄積された経験・知見・事例を「教材」化し、彼ら自身が「講師」として庁内での勉強会を主導するなど、組織を巻き込む活動が期待されます。 これにより活用を定着させ、最終的にはそれらのナレッジを「自治体の情報資産」として組織に残していくことを構想しています。
大きな可能性と、「体験」という最初の一歩
私たちは、この「内部に教育者を育て、仕組み化する」というアプローチが、自治体におけるDX推進の強力なモデルケースになるのではないかと期待しています。
特に今回のプロジェクトは、全国の自治体と繋がりを持つ組織との取り組みであり、この構想が成功すれば、多くの地方が抱える共通課題(担い手不足など)の解決に貢献できる、大きなポテンシャルを秘めていると考えています。
この記事をお読みの自治体職員の皆様も、まずは「自走」に向けた第一歩として、ご自身の組織の「見えない壁」は何かを見つめ直し、フェーズ1の「安全に体験する」ことから始めてみてはいかがでしょうか。






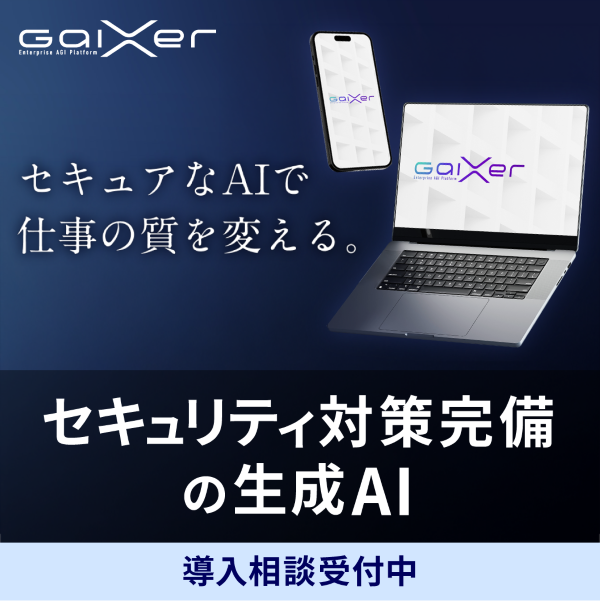
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)