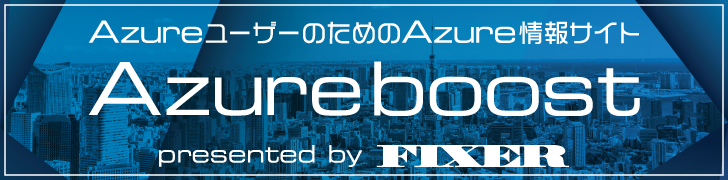はじめに
先日、順当に生きていると自分の年次ではお目にかかれないような貴重な方とのお打合せに同席させていただきました。生成 AI やロボティクスの進化により、業務の自動化や効率化が急速に進んでいます。しかしどれだけ技術が発展しても、人と社会を支えるのは人間性です。私たちの議論では「人のために何ができるか」「利他の心が企業や組織をいかに強くするか」といったテーマが繰り返し語られました。
そのとき挙げられたのが、日本資本主義の父・渋沢栄一の幼少期の逸話です。商売と慈善の境界を教えるこの物語は、今も企業や個人が持つべき姿勢を示しています。本記事ではその逸話を紹介しながら、真の人間性について考えます。
渋沢栄一「三俵の米」の逸話
渋沢栄一は、武蔵国の農家に生まれました。10歳のある日、母から「近所の家が病気で困っているから、お米を分けてあげなさい」と言われます。栄一は言われた通り、家の米蔵から3俵もの米を持ち出して隣人に渡しました。もらった家族は涙を流して喜びましたし、栄一も良いことをしたと思っていました。
ところが年末、家の米蔵が空になってしまいます。餅つきに必要な米が足りず、父の市郎右衛門が言いました。
「栄一、お前は良いことをした。だが、良いことをしたせいで、わしらの家族が困ることになった。人を助けたいなら、まず自分が強くならなければならない。弱い者が弱い者を助けようとしても、共倒れになるだけだ」。
幼い栄一にはこの言葉の意味がすぐには理解できませんでした。その答えを得たのは17歳のとき。父に託されて藍玉を売りに行った際、いつも世話になっている商人に「長く付き合いたいから」と頼まれ、通常より安い値段で販売してしまいます。さらに支払い期日の延期にも応じた結果、その商人が破産し代金が回収不能になりました。このときも父は厳しく叱責します。
「栄一、お前は商売を何だと思っている?慈善事業か。困っている人を助けるのは悪いことではない。だが、それで自分の家族が困ることになれば本末転倒だ。お前の親切は、その商人を本当に助けることになったのか? 正当な値段で売っていればその商人はもっと真剣に経営を考えたかもしれない。お前の優しさが、その商人をダメにしたのかもしれないぞ」。
この経験から栄一は、**“情に流されて自己犠牲に陥ることは、相手にとっても自分にとっても良い結果を生まない”**と学びます。商売と慈善の違いを理解した上で、社会に貢献するためには自らが強くなることが前提だと気付いたのです。
商売と慈善の境界―まず基盤を整えること
渋沢栄一の逸話は、企業や個人が社会貢献を考える上で重要な視点を与えてくれます。
まず自分たちの基盤を整えること: 収益が不安定な状態で多額の寄付や支援を行えば、組織全体が共倒れになりかねません。組織として安定した収益や生産性を確保して初めて、他者への貢献が持続可能になります。
自分の裁量で稼いだ中から利他を実践する: 渋沢家の父は「他人の資源を勝手に持ち出して助けるのは本末転倒だ」と教えました。会社でも、赤字を出しながら地域貢献活動を行うのではなく、利益の一部を活用して社会の課題解決に取り組むことが重要です。
- “甘やかし”は相手の成長を妨げる: 安易な値引きや援助は相手の自立を阻害し、結果的に相手をダメにしてしまう場合があります。本当に相手のためを思うなら、時には厳しい決断も必要です。
これらは経営者にとってだけでなく、従業員一人ひとりにも当てはまります。限られた時間とエネルギーをどこに投資し、誰のために使うのかを考える際、まず自分が強くなることが他者への本当の支援につながるのです。
真の人間性とは「人のためにを最優先できる心」
会議では、リーダー育成の場面で次のような議論がありました。ある参加者は、人間性の定義について「難しい言葉はいらない。“誰かのために”を最優先できる人が、人間性の高い人だ」と述べました。
しかしこの「誰かのために」は、単にいい人ぶることではありません。人を助けたいという気持ち自体は尊いものの、無計画な善意や自己犠牲では長続きせず、むしろ相手の成長を阻害してしまいます。だからこそ私たちはまず自分の能力や資源を高め、それを最大限に活用して他者に貢献する姿勢を持つ必要があります。
議論では、追い込まれた時ほど自分を優先しがちになるが、そんな時にこそ周囲のために動ける人が尊敬されるという意見もありました。利他の心は、日々の小さな行動を通じて鍛えられるものであり、与えられた環境の中でいかに他者に貢献できるかを意識することが、人間性を高める鍵だと語られていました。
AI時代にこそ問われる人間性
AIエージェントや自動化技術が進む今、私たちの仕事は大きく変わりつつあります。単純作業はAIが担い、人は創造力やコミュニケーション、倫理的判断が求められる領域にシフトしていきます。こうした時代において、技術を扱う側の人間性がより重要になります。
渋沢栄一の逸話から学ぶべきは、技術や商売の手段と人を思いやる心のバランスです。AIの導入で生産性が上がった分、私たちは自分自身や組織をより強く、持続可能なものにし、その上で社会に貢献していく必要があります。自らの基盤を築きながらも、誰かのために何ができるかを常に問い続ける。この姿勢こそが「真の人間性」であり、AI時代のリーダーシップに不可欠な要素だと言えるでしょう。
おわりに
渋沢栄一が少年時代に学んだ教訓は、現代の私たちにも色褪せることなく響きます。無自覚な善意は自分をも相手をも困らせる。だからこそ、自分自身や組織の基盤を整え、その上で利他的な行動を取ることが重要です。そして「誰かのためにを最優先できる心」を持ち、持てるものを最大限に生かして他者に貢献することが真の人間性であると改めて確認しました。
私たちは今後も技術革新とともに変化する環境の中で、この教訓を胸に、自らの力を高めつつ他者へ貢献する企業文化を育てていきたいと考えています。






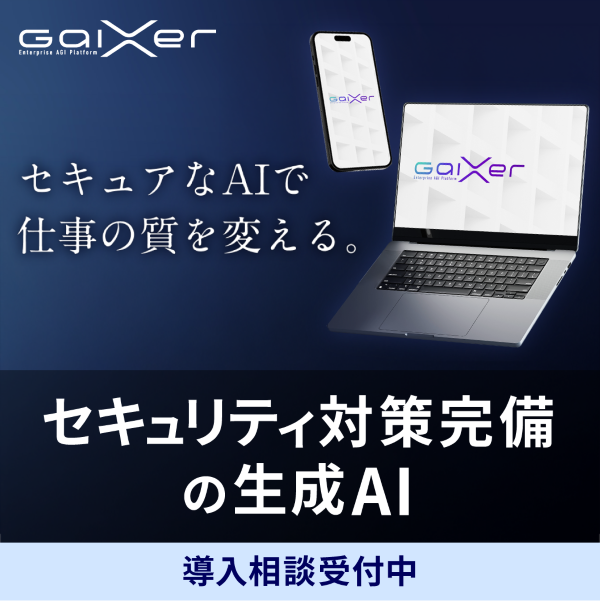
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)