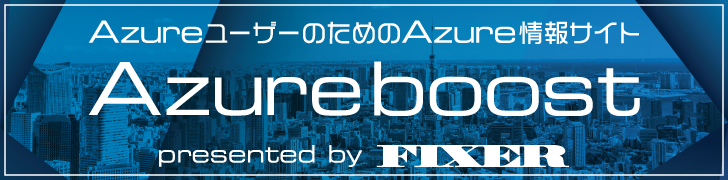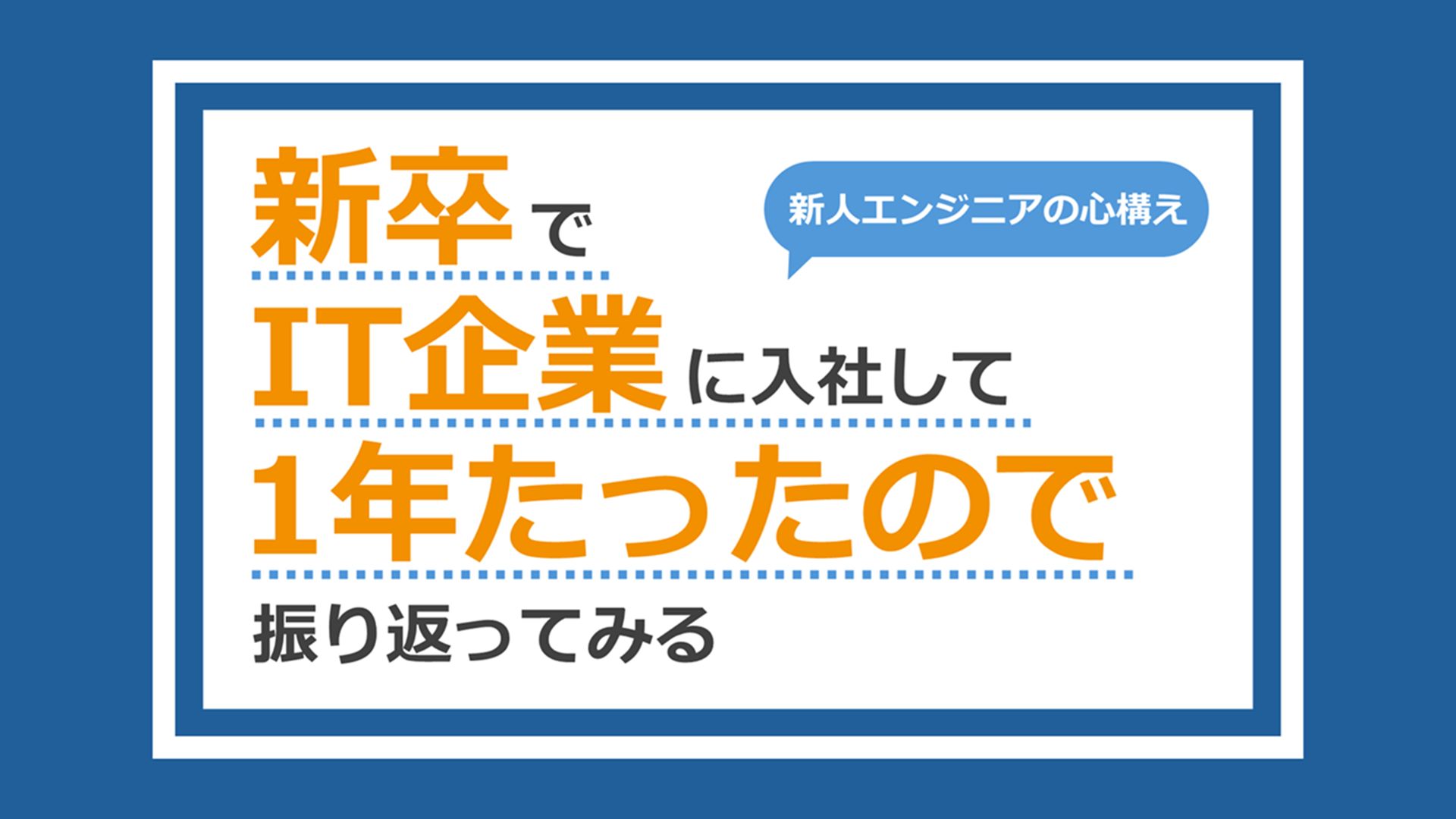
はじめに
お疲れ様です。
24年度に入社した江藤です。
私は新卒としてFIXERに入社し、あっという間に1年が過ぎました。
期待と不安でいっぱいだった入社当初を思い返すと、たくさんのことを経験し、
様々な面で学ばさせていただいた1年だったと実感しています。
この記事では私が新卒エンジニアとして経験した
1年間の振り返りと気づき・学びについてまとめてみたいと思います。
同じように新卒のエンジニアとして奮闘している方や
これからエンジニアを目指す方の参考になれば幸いです。
業務経験
入社後の1年間で主に3つのプロジェクトに携わる機会がありました。
- システムの運用・保守(の手伝い)
- インフラの開発(の手伝い)
- システムの開発
システムの運用・保守
入社して最初に配属されたのは、稼働中のシステムの運用・保守を行うプロジェクトでした。
お客様からの不具合報告への対応や機能改善のテスト実施、
ドキュメント作成などを担当させていただきました。
インフラの開発
次に新規システムのインフラ開発を行うプロジェクトに参加しました。
クラウドサービスを利用したインフラ構築において、IaCでの管理や、
可用性を考慮したインフラ設計の考え方について学ばさせていただきました。
システムの開発
次に新規WEBシステムの開発を行うプロジェクトに参加しました。
フロントエンドの主要な実装を担当させていただき、
フレームワークを利用したコンポーネント設計から実装、
API設計や認証・認可設計など幅広く携わらせていただきました。
仕事面での気づき・学び
SOSの出し方を知ろう

「エンジニアが勉強すべき言語は日本語である」という言葉をよく耳にしますが、
実際にその通りだと実感しています。
働き始めて特に重要だと感じたのは、進捗報告の重要性です。
入社当初は、行き詰っていても報告や相談をためらうことがありました。
いえ、正確には、「報告や相談のやり方が分からなかった」が正しいかもしれません。
私自身、先輩方から
「今どんなことで困っているのか、次に何をしようとしているのか、
それを共有してくれないと私たちも助けようがないんだよ」
とアドバイスをいただき、考え方が大きく変わりました。
それ以降は、以下のことを意識して報告するように心がけています
- 現在取り組んでいる作業の状況
- 直面している技術的な課題
- 次に予定している作業内容
- 他メンバーにサポートしてほしい部分 など
特にチャットやチケットなど、テキストベースで記録を行うようになってからは、
先輩方からより具体的なアドバイスをいただけるようになりました。
また、後から自分の作業を振り返る際にも、
当時の状況や判断の経緯を確認できる重要な資料になっています。
エンジニアという職種は、一見すると個人での作業が多いように思えます。
しかし実際には、チームでの協力が不可欠です。
いくら技術力が高くても、自分の状況や考えを適切に伝えられなければ、
チームの一員として十分な力を発揮することはできません。
技術スキルの向上と同様に、コミュニケーション能力の向上も、
エンジニアにとって重要な課題なのだと理解できました。
郷に入っては郷に従え

「郷に入っては郷に従え」ということわざがありますが、
これは開発現場でも非常に重要な考え方だと実感しています。
入社当初は「コードは動けば良い」「自分が書きやすい方法で」と考えがちでしたが、
チーム開発において、それは大きな間違いでした。
例えば、命名規則、インデント、コメントの書き方など
一見些細に見える規則でも、定められたルールには必ず理由があります。
特に印象的だったのは、先輩から
「この規則は、今のあなたには過剰に思えるかもしれない。
でも、これは何人もの開発者が関わり、
長期的にメンテナンスしていくプロジェクトだからこそ必要なんだ」
と教えていただいたことです。
実際、チームの規則に従ってコードを書くようになってからは、
レビューでの指摘が減り、他のメンバーからのコードの理解も早くなりました。
また、自分が書いたコードを後から見返した時にも、理解がしやすくなっていることに気がつきました。
先述したように、直近では新規プロジェクトの設計段階から参加させていただく機会があり、
逆の立場として郷(規則)を作る側の経験もできました。
コーディング規約やディレクトリ構成、命名規則など、一つ一つのルールを決める過程で、
将来の保守性や拡張性を考慮しながら決定していくことの難しさを痛感しました。
この経験を通じて、既存の開発規則への理解がより一層深まったように感じています。
個人開発と違い、チーム開発ではコードは共有の資産です。
その意味で、開発規則は単なる「縛り」ではなく、
チーム全体の生産性を高めるための重要な基盤なのだと理解できました。
生成AIと責任
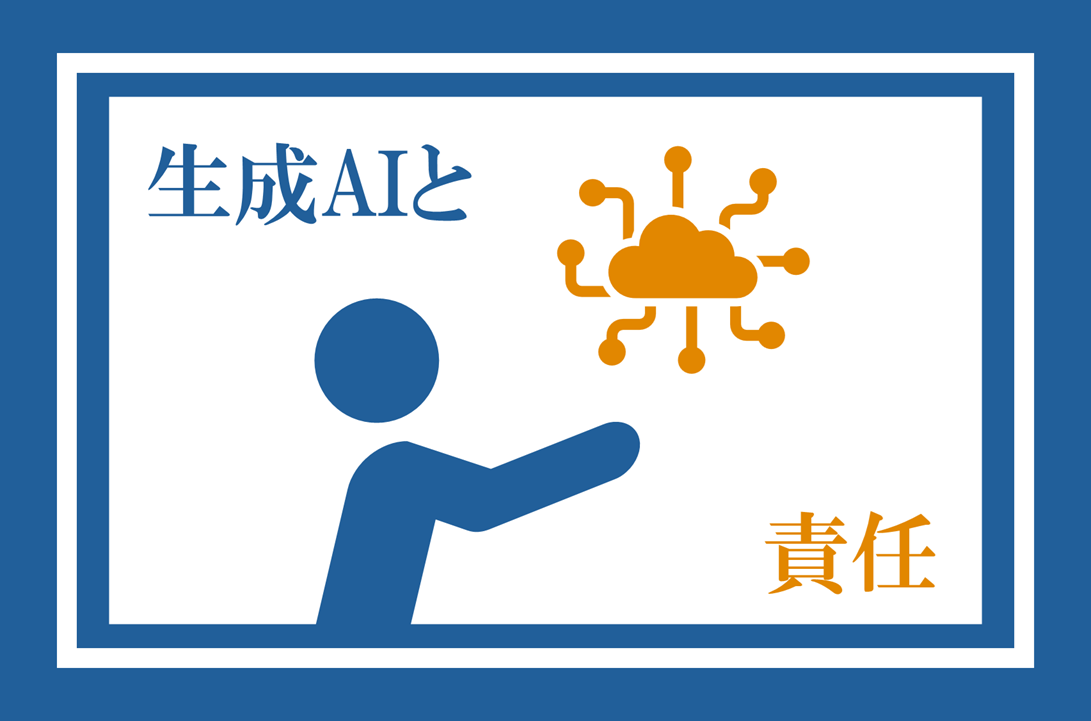
エンジニアとしての働き方において、ChatGPTなどの生成AIの活用は当たり前になりつつあります。
私も日々の開発において、自社提供しているGaiXerを活用しています。
そのうえで、重要だと感じているのは
「理解していないコードをコピー&ペーストしない」
という原則です。
AIは確かに優れたコードを提案してくれますが、
その動作原理や意図を理解していなければ、
バグが発生した時の対応や、機能改修時に大きな問題となります。
実際、AIが生成したコードをそのまま使用して後から苦労した経験があります。
表面上は動作していても、パフォーマンスやセキュリティの問題を含んでいる場合があります。
そのため今では、AIを「コードを書くためのアシスタント」ではなく、
「より良いコードを学ぶための教材」として活用するように心がけています。
また、最終的にコードの責任を取れるのは開発者である私たちです。
AIは便利なツールですが、あくまで「ツール」に過ぎません。
コードの品質、セキュリティ、保守性に関する判断と責任は、
エンジニアである私たちが担う必要があります。
このように、AIは非常に強力な開発支援ツールですが、
それを適切に活用するためには、基礎的な技術力とエンジニアとしての判断力が不可欠だと実感しています。
新しい技術との向き合い方

私は先述したように様々なプロジェクトに参加させていただきました。
言語だけでもHTML、TypeScript、CSS、Java、Shell、Python、SQL など
多くの技術に触れる機会がありました。
当初は新しい技術への不安もありましたが、実際に手を動かしていく中で様々な気づきが得られました。
学生を卒業したからといって、学びが終わるわけではなく、
むしろ現場では技術の進化に常にキャッチアップしていく必要があります。
普段使用しているサービスや言語、フレームワークも日々アップデートされ、
新しい機能や仕様が追加されていきます。
しかし、恐れる必要はありません。
むしろチーム開発において、誰かが初めて触る技術があるのは当然のことで、
それを知見として共有し、今後に生かしていくことが重要であると感じています。
「分からない」ことは決して恥ずかしいことではなく、
エンジニアとしての日常の一部として、前向きに取り組んでいく必要があります。
メンタル面での気づき・学び
みんな人間

チームメンバーも、先輩方も、そして自分自身もみんな人間です。
人間である以上、完璧ではありません。
疲れがたまれば集中力が低下して不具合が発生するコードを書いてしまったり、
心身の疲労でイライラしてしまったり、
単純なうっかりミスをしてしまうことがあります。
最初はこういった状況に遭遇するたびに気にしすぎていましたが、
これらは避けられない現実として受け入れることが大切だと学びました。
むしろ重要なのは、ミスを責めるのではなく、
それをチームとしてどうカバーしていくか、
どうすれば防げるのかを考えることです。
レビューでのダブルチェックや、困ったときに気軽に相談できる雰囲気づくり、
体調管理の声がけなど、お互いをサポートできる関係性が
チームの強さに繋がっていくのだと実感しています。
怒ること

開発の現場では、設計の方針やコードの書き方について、時に意見が衝突することがあります。
これは当たり前のことで、むしろ健全な状態だと考えています。
なぜなら、自分の「当たり前」は、必ずしも相手にとっての「当たり前」ではないからです。
大切なのは、そういった状況での向き合い方です。
相手の意見を一方的に否定するのではなく、なぜその考えに至ったのかを丁寧に聞くようにしています。
経験上、相手にも必ずその結論に至った理由や背景があり、
それを理解することで、より良い解決策や折衷案が見つかることが多いです。
感情的になってしまうのは人間として自然なことですが、その矛先を間違えないことが重要です。
本当に怒るべきなのは、セキュリティ違反やコンプライアンス違反、
意図的な隠蔽行為など、プロジェクトやチームの信頼関係に関わる重大な問題の時です。
これらに該当しない限り、怒る必要はないと思います。
おわりに
改めて入社してからの1年間を振り返ってみると、
技術面での成長はもちろん、エンジニアとしての考え方や仕事への向き合い方について
多くの事を学ばせていただきました。
しかし、まだまだ学ぶべきことは多く、これからも新しい課題に直面することと思います。
この1年間で得た経験と気づきを大切にしながら、さらなる成長を目指していきたいと考えています。
今年度は実務で使用していた技術についての理解を深めたり、資格の取得に励めればと思います。
最後に、日々支援してくださる先輩方、共に成長を目指す同期、
そして貴重な機会を与えてくださった会社に、心から感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします!






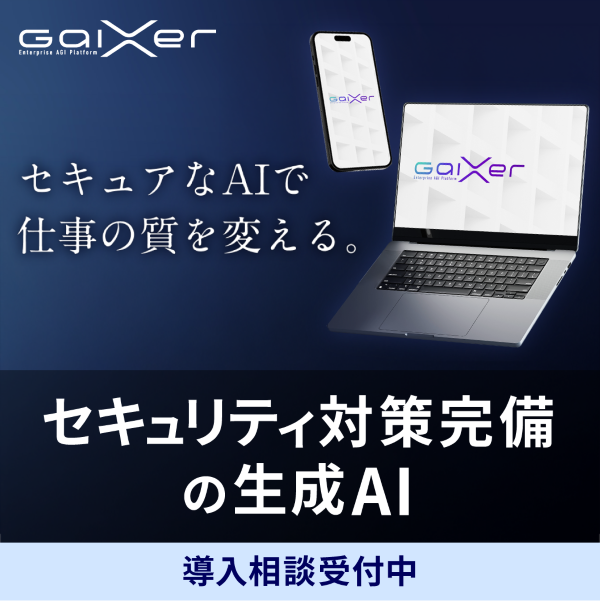
![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)
![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)
![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)